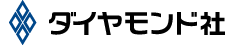成功はすべてコンセプトから始まる
「思い」を「できる」に変える仕事術
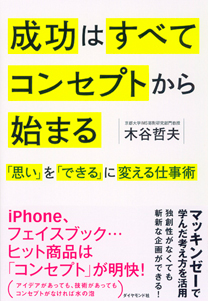
成功はすべてコンセプトから始まる
「思い」を「できる」に変える仕事術
書籍情報
- 木谷哲夫 著
- 定価:1650円(本体1500円+税10%)
- 発行年月:2012年09月
- 判型/造本:46並製
- 頁数:200
- ISBN:978-4-478-02157-6
内容紹介
iPhone、フェースブック等々、ヒット商品はすべてコンセプトが光っている。アイデアがよくても技術があっても、コンセプトがなければ水の泡。独創性がなくたって、斬新な企画はできる!日本人が弱いと思われがちな「コンセプト立案力」の身につけ方を、「マッキンゼー」出身の著者がわかりやすく解説する!
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
序 章 「コンセプト自由競争」の時代が来た
1 なぜ、コンセプトが必要なのか
いまの状況から、一段「上」に抜けるために
「コンセプト自由競争」の時代が来た
ロジカル・シンキングは万能ではない
組織の立て直しにもコンセプトは必要
良いコンセプトのつくり方
ぞくぞくするような知的快感を手にしよう
第1章 実現可能性より面白さコンセプト・ドリブン思考
1 インパクトがすべての原動力
インパクトを実現するまでの、2つの道筋
コンセプト・ドリブンvs.実現可能性ドリブン
トヨタの「カイゼン」は、実現可能性ドリブンではない
良いコンセプトは、優先順位をはっきりさせる
お役所がらみのベンチャーが成功しないわけ
技術力だけでも、やはりうまくいかない
インパクトと実現可能性は、トレードオフの関係にある
2 コンセプトの効果
良いコンセプトは、面白さと説得力を併せ持つ
良いコンセプトは人を束ねる
わかりやすいコンセプトでハードルを乗り越える
パズルがきっちりハマった感じ
第2章 良いコンセプトを生むクリエイティブ思考の技術
1 オリジナリティ幻想を打ち破れ
アイデア出しは、ハードルを上げすぎると失敗する
オリジナルより、「リソースフル」を目指そう
事実を正しく見ること、疑うこと
「疑う」と「つくる」、2つの能力を同時に使う
クリエイティブさは、才能ではなく蓄積
既存のものの組み合わせで、発想は無限に広がる
有望な組み合わせは、一瞬でイメージが伝わる
2 組み合わせ能力を鍛える
組み合わせ能力を高める6つのポイント
視点を垂直方向に動かす
視点を水平方向に動かす
普段と違う環境をいかにつくるか
創造性をアップさせる「10の具体的方法」
第3章 アイデアをおカネにするビジネスモデル発想法
1 持続可能性が「あるべき将来像」のカギ
成功する人はなぜ、「根拠のない思い込み」を持っているのか
きちんと事業として成り立つかどうか
おカネのことは後回し、では続かない
2 ビジネスモデルの「三本柱発想法」
ビジネスモデルの基本要素は3つだけ
日本で衰退産業の漁業は、ノルウェーでは高収入職種
ビジネスモデルに必要な要素を、1枚にまとめる
三本柱発想法で成功事例を読み解く
MBA的方法論と何が違うのか
3 顧客開発からはじめよう
最大のリスクは、顧客が存在しないこと
意見を聞くのではなく、本物の支持者を探す
新しい顧客の「かたまり」を発見する
4 約束を守れる「根拠」を構築する
根拠=自社の強み、ではない
強みを生かすのではなく、どうやったら勝てるかで発想する
演習問題 緊迫の町おこしプロジェクト
第4章 本気の仲間を増やすコミュニケ—ション術
1 コミュニケーションの基本ステップ
仲間がいなければ、何も始まらない
ステップ① 一行コンセプトをつくる
ステップ② 物語化する
ステップ③ 資料をつくる
パワポに頼らず、シンプルに勝負する
ステップ④ 自分を伝える
徹底して、一分の隙もなく「本気度」を示す
本当に伝えたいことに集中する
2 コンセプトのコミュニケーションとは、楽観論を売ること
楽観論を売りつつ、冷めたマインドをキープする
自分が評論家でないことを示す
プロセス自体を楽しもう
終 章 強い意志がコンセプト実現を可能にする
1コンセプトには強い意志が不可欠
「見えている人」は何が違うのか
忙しさの中で、失われてしまうもの
モチベーションだけでは乗り切れない
良いコンセプトを持つ人についていく手もある
インパクト=コンセプト+意志力
あとがき
参考文献
著者
木谷哲夫(きたに・てつお)
マッキンゼー・アンド・カンパニーに10年間在籍。アナリストとして入社しアソシエート・プリンシパルとして卒業するまで、グローバルなチームで金融機関、自動車・機械・ハイテク・通信業界における数多くの新規事業戦略立案、業務改善プロジェクトを手がける。
日本興業銀行で企業金融業務、アリックス・パートナーズで企業再建業務に従事。
2007年より京都大学産官学連携本部 イノベーション・マネジメント・サイエンス(IMS)寄附研究部門教授として、起業家教育を担当。
大阪府・市の特別参与を兼務(府市統合本部)。東京大学法学部卒、シカゴ大学政治学大学院(MA)、ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA。