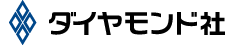QUEST「質問」の哲学
「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす
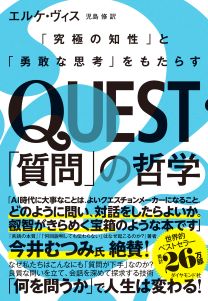
QUEST「質問」の哲学
「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす
書籍情報
- エルケ・ヴィス 著/児島 修 訳
- 定価:1980円(本体1800円+税10%)
- 発行年月:2025年03月
- 判型/造本:46並
- 頁数:408
- ISBN:9784478120606
内容紹介
哲学者ソクラテスが実践した「質問の技法」を獲得することで、思考を深め、本当の知性を育む会話ができるようになる本。自分の意見を押しつけず、相手から深い意見を引き出す「正しい質問」のスキルが身につく。他人と深く意見を交わすことより、より豊かな人生を送れるようになる。累計26万部の世界的ベストセラー!
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに
運命の昼休み
現代人の人生がつまらない理由
下手な質問は地獄をつくる
「何を問うべきか」を問わなければならない
勇敢に思考し、深く探求する
ソクラテスに学ぶ「質問の哲学」
ソクラテス ── 最も実践的な哲学者
「私は何も知らないことを知っている」
真の知識は「対話」でしか得られない
「探求する態度」を取り戻す
なぜ現代人に「質問の哲学」が必要なのか?
第1章 なぜ私たちは良い質問をするのが下手なのか?
▼「良い質問」ができない私たち
「本当に良い質問」をするために学ぶべきこと
そもそも質問とはいったい何なのか?
「悪い質問」と「良い質問」
「深い会話」とは何か?
「良い質問」ができない6つの理由
▼良い質問ができない理由1 ── 人はそもそも自分の話をしたがる
話を遮る、まくし立てるように話す、自分の意見を何度も繰り返す
相手が話をしているあいだに、自分が言うことを考えている
反射的にアドバイスを与えようとする
「私も同じことをしたことがある!」と言う
自分のことを話すのは気分がいいが、質問をするのはそうではない
▼良い質問ができない理由2 ── 尋ねるのが怖い
なぜ質問をするのが怖いのか?
自分の基準で話題を選んでしまう
波風を立てたくない
本当の質問をしない文化
▼良い質問ができない理由3 ── 良い印象を与えたい
質問をする人は自信がない?
脳は「じっくり考える」のが苦手
オピニオンリーダーではなく、クエスチョンメーカーになる
▼良い質問ができない理由4 ── 客観性の欠如
私たちは理性ではなく直感で意見している
「反対」は「平手打ち」されるのと同じ
自分の信念に向き合い、深く掘り下げる
▼良い質問ができない理由5 ── 忍耐力がない
良い質問をするのは時間の無駄?
1分間考えてから質問する
▼良い質問ができない理由6 ── そもそも方法を知らない
良い質問をする方法は、誰も教えてくれない
私たちの探求心が失われる理由
質問を避ける理由を自覚する
第2章 質問の態度
▼「自分は何も知らない」という態度で疑問をもつ
内なるソクラテスを目覚めさせる
ソクラテス的な態度とは何か?
ソクラテス的な態度の鍛え方
自分の思考を観察する訓練
「何について怒るか」で自分を知る
▼不思議(ワンダー)の感覚を大切にする
「不思議」とは「選択」である
日常に「不思議のための空間」をつくる
▼好奇心 ── 本心から「知りたい」と思う
会話中に自分のことしか考えていない
「相手のことはわからない」と認める
「それ、私もしたことがある」と思ってしまう
好奇心を育む方法 ── 私は初心者、あなたは専門家
▼質問をするためには「勇気」が必要だ
「デリケートな質問」がつながりを深める
思い切って質問することの大切さ
▼自分の判断を絶対的なものだと思わない
私たちの「判断」は的外れ
判断を留保せずに「引っ込める」
人間万事塞翁が馬 ──「良いか悪いかは、誰にもわからない」
判断せずに、ただ観察する
▼観察と解釈の違い
「ただ観察すること」の難しさ
デカルトに学ぶ「知らないこと」に耐える方法
「何もしない」ことをする
「疑念」と「無知」の違い
5分間だけ無知に向き合う
▼共感を棚上げする
「共感」が役に立たない理由
「認知的共感」と「感情的共感」
「共感的中立性」を保つ
相手に共感するより大切なこと
人生の問題を哲学的に探求する
偽の言葉で心を落ち着かせてはならない
たった一つの質問が健全な結論を導く
勇気を出して自分の考えを疑う
▼ソクラテス的な反応を身につける
同調圧力に負けず少数派を尊重する
極端な意見にも判断を下さない
相手の苛立ちに耐える
▼ソクラテス式問答法の構造
ソクラテス式問答法は、一つの哲学的な問いから始まる
抽象的な概念を現実に当てはめる
さらなる探求と質問を生み出す
「定義づけの罠」に陥らない
思考のプロセスを巻き戻す
▼「合意」に向けて努力する
結論ではなく「合意」を目指す
エレンコス ── 相手から感情的に反応される
「会話を続けたい? それとも終わらせたい?」
アポリア ──「これ以上はわからない」に到達する
ソクラテス的態度のまとめ
第3章 質問の条件
▼質問の条件1 ── すべては聞き上手になることから始まる
良い質問は「良い聞き方」から生まれる
話を聞くための3つの姿勢
・話を聞く1つ目の姿勢=「私はこれについてどう思うか?」
・話を聞く2つ目の姿勢=「それは、あなたにとってどういうことだろう?」
・話を聞く3つ目の姿勢=「私たちはそれをどうとらえるべきか?」
▼質問の条件2 ── 言葉を大切にする
ちょっとした言葉選びに本音がでる
シャーロック・ホームズのように推理する
言葉と表層的リスニング
ボディランゲージを解釈する
▼質問の条件3 ── 許可を求める
「質問してもいいか」を事前に確認する
哲学的な探求に招待する
▼質問の条件4 ── ゆっくり対話する
時間をかけて、時間がかからないようにする
▼質問の条件5 ── フラストレーションを許容する
フラストレーションが対話の燃料になる
第4章 質問の技法
▼「上向きの質問」と「下向きの質問」を使いこなす
「上向きの質問」と「下向きの質問」とは?
「良い母親」とは何か?
▼「下向きの質問」の後に「上向きの質問」をする
論点がずれないように質問する方法
「クリティカルポイント」に達する質問
「怠け者」とはどのような人か?
▼良い質問のためのレシピ
「オープン・クエスチョン」は良い質問なのか?
質問が「オープン」か「クローズド」かを見分ける方法
クローズド・クエスチョンを効果的に使う
「なぜ」は攻撃に使われている
「なぜ」と「どのように」を使い分ける
▼質問に答えてもらいやすくなる魔法のフレーズ
「教えて」がもたらす奇跡
▼質問の落とし穴とその回避策
質問はテニスのようなもの
そのまま言えばいいのに、なぜ質問にするのか?
・質問の落とし穴1 ── ルーザー・クエスチョン
・質問の落とし穴2 ── でもクエスチョン
・質問の落とし穴3 ── カクテル・クエスチョン
・質問の落とし穴4 ── 曖昧な質問
・質問の落とし穴5 ── 根拠のない二者択一の質問
・質問の落とし穴6 ── 中途半端な質問
第5章 質問から会話へ
▼「良い質問」から「良い会話」へつなげる
良い会話はドミノゲームのようなもの
「質問」と「答え」がつながっているかを確認する
「イエスかノー」で答える
「簡潔に話す」のが良い会話のルール
▼質問へのフォローアップ
フォローアップ・クエスチョンとは?
フォローアップの前提は注意深く話を聞くこと
「自明のこと」について質問する
フォローアップの2つの方法
エコー・クエスチョン ── フォローアップの最もシンプルな方法
良いエコー・クエスチョンをするコツ
概念をフォローアップする
▼相手の発言の真意を問う
「それは具体的には何を意味するのか?」
「真意を問う」質問の方法
▼フォローアップの方法 ── カンフル剤としての「もしも」の質問
自分の中に隠れている考えを発見する
▼自分の考えに疑問をもつ
では、いつ自分の意見を言えばいいのか?
相手とのあいだに橋を架けてから意見を伝える
無関心な人との会話もおそれる必要はない
おわりに
謝辞
訳者あとがき
原注
著者
エルケ・ヴィス(Elke Wiss)
わずかな考え方の変化で日常生活を大きく改善できる「実践哲学」の国際的なベストセラー作家。戯曲・短編小説・モノローグ・物語的な哲学詩の執筆や演出、記事の執筆、ポッドキャストの制作なども手がけ、トレーナー、ファシリテーター、実践哲学者としても活動。実践哲学と質問術のワークショップを主宰し、企業内でのソクラテス式問答法の活用方法の指導や、個人向けの哲学相談も行っている。本書が初めての著作。
訳者
児島 修(こじま・おさむ)
英日翻訳者。立命館大学文学部卒(心理学専攻)。おもな翻訳書に『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』『サイコロジー・オブ・マネー 一生お金に困らない「富」のマインドセット』『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』『勘違いが人を動かす 教養としての行動経済学入門』(以上、ダイヤモンド社)などがある。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)