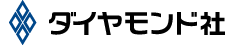取引先から信頼される 日本発サイバーセキュリティ基準

取引先から信頼される 日本発サイバーセキュリティ基準
書籍情報
- 藤田哲矢 著
- 定価:2200円(本体2000円+税10%)
- 発行年月:2025年11月
- 判型/造本:46並
- 頁数:248
- ISBN:9784478118085
内容紹介
サイバーセキュリティインシデントは業界・規模を問わず同時多発的に発生し、従来の常識が通用しない時代になりました。経営者が本当に安心できるサイバーセキュリティ対策とは何か?5段階の評価フレームワークをもとに、企業の実情に合った取り組みと投資対効果の考え方を分かりやすく解説します。
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに
◼高度化・組織化が進むサイバー犯罪にどう対応するか
◼ISMSを自社のセキュリティ対策に活かすには
第1章 日本の情報セキュリティの実情
1 日本のセキュリティ対策が遅れている理由
◼サイバー能力において日本は世界16位という現実
◼性善説に基づく支え合いの精神はサイバー空間では通用しない
◼「日本語のバリア」はすでに効果を失いつつある
2 組織、人材、そして何よりも経営者の意識改革を
◼セキュリティ対策は〝コスト〟なのか
◼セキュリティ責任者の設置率は米豪の半分以下
◼人材不足に対して強化策を行っている企業はわずか
◼経営者はセキュリティにどこまでコミットすべきか
◼「セキュリティは経営マター」の認識が必要
3 実効性のあるセキュリティ体制を構築するには
◼日本企業がセキュリティ人材確保・育成に本腰を入れない原因
◼サイバー脅威とISMSの30年
◼ISMS取得だけでは対策は十分ではない
◼具体的なセキュリティ対策で海外企業と如実な差
◼日本企業はISMS偏重?
◼アメリカで生まれたNISTとCMMC
◼中長期的なセキュリティ対策計画の策定と定期的な評価を
第2章 なぜいまセキュリティが重要なのか
1 サイバー攻撃の歴史と転換点
◼サイバー空間の攻撃と防御の歴史を知る意味
◼当初の攻撃は愉快犯が中心だった
◼2000年前後から始まったサイバー攻撃の目的と質の変化
2 ビジネスへの脅威としてのサイバー攻撃
◼攻撃者はそれなりのコストをかけている
◼2010年代から増え始めた標的型攻撃
◼世界中で増加するランサムウェア攻撃
◼コロニアル・パイプラインへの攻撃と身代金
◼人の命を脅かす、病院へのランサムウェア攻撃
◼ビジネスメール詐欺の脅威
◼「悪意あるAIツール」によるサイバー攻撃の増加
〈コラム〉サイバー攻撃が増加する中での日本の法規制
3 情報セキュリティの誕生とその後の変遷
◼初期の対策としての「ファイアウォール」と「アンチウイルスソフト」
◼攻撃を水際で防ぐ「境界型防御」が主流に
4 サイバー攻撃の「高度化」に立ち向かう
◼攻撃の質的変化はなぜ起こったのか
◼デジタルによる利便性は攻撃者も享受している
◼「産業化」するサイバー攻撃
◼ゼロデイ攻撃が狙うソフトウェアの脆弱性
◼サイバー攻撃は気づかれないように行われる
5 IT活用/IT環境の変化とセキュリティ対策
◼クラウド活用の広がりと求められる対策
◼テレワークの普及で浮上した境界型防御の課題
◼ゼロトラストセキュリティという潮流
◼セキュリティ業務の自動化・省力化
第3章 真に効果のあるセキュリティ対策を行うには
1 自社のサイバーセキュリティ対策の現状を知る
◼5段階でのセキュリティ対策レベル
◼最低限の対策を施す:初級レベル・一つ星
◼個人・組織ともに対策を高度化:初中級レベル・二つ星
◼自社を守るだけではセキュリティ対策は道半ば
◼企業・組織のセキュリティ対策の基本となるNIST CSF
◼サプライチェーン企業が最低限実装すべき対策:中級レベル・三つ星
◼自社の役割を踏まえて事業継続性を確保:中上級レベル・四つ星
◼三つ星と四つ星のどちらを目指すべきか
◼セキュリティの透明性と予見性を兼ね備える:上級レベル・五つ星
2 成熟度を上げるためにはどのようなアクションを取るべきか
◼セキュリティ成熟度向上のための5つのステップ
◼なぜ経営層が正しく理解するのが難しいのか
第4章 セキュリティ投資はいかに行うべきか
1 日本企業のセキュリティ投資の問題点
◼多種多様なリスクを同じ尺度で評価する
◼セキュリティリスクへの対応が重要視される理由
◼「セキュリティ投資額は連結売上高の0・5%以上」という考え方
◼ビジネスへの影響から対策を考える
◼KADOKAWAへの攻撃に見る被害の多様性
◼ランサムウェアの脅威は以前から指摘されていた
2 セキュリティ投資の基本的な考え方
◼ROSIをベースに対策の優先順位を判断する
◼ケース1:ランサムウェア攻撃への対策
◼ケース2:製造業におけるランサムウェア攻撃への対策
◼ケース3:個人情報漏洩対策
◼ケース4:セキュリティ保険の落とし穴
◼IPAが無償提供する「NANBOK」
3 セキュリティ投資で経営者が果たすべき役割
◼経営トップの3つの役割
◼リスクの軽減・移転・回避
◼「不確実性」にどのように対応するか
第5章 サプライチェーン攻撃をいかに防ぐか
1 日本企業のサプライチェーン防御は道半ば
◼チェーンの強度は「最も弱い輪」が規定する
◼サプライチェーン攻撃の3タイプ
◼サプライチェーンに対する統制は十分か
2 サプライチェーン全体でセキュリティを強化するには
◼サプライチェーンセキュリティ強化に向けた国の施策
◼経済産業省が進める評価制度づくり
◼サイバーセキュリティガイドライン:自動車産業を例に
3 サプライチェーンセキュリティ強化に役立つツール
◼ソフトウェアの部品構成を示すSBOMの重要性
◼アンケート調査の限界とツールを活用した可視化
◼サプライチェーン内で互いに知見を高め合う
おわりに
著者
インフォセックアドバイザリー株式会社 代表取締役 藤田哲矢
一橋大学大学院商学研究科、INSEAD(欧州経営大学院)のAMPを修了。ソフトバンク、アクセンチュア、メイソンコンサルタントグループを経て、インフォセックアドバイザリー(旧称メイソンコンサルティング)を設立。同社において製造業やハイテク産業のグローバル企業を中心にサイバーセキュリティのアドバイザリーや監査業務に従事。近年では、グローバルのサイバーセキュリティ・コンソーシアムに参画しサプライチェーン・セキュリティの活動を推進。また、日本国内のサプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム(CRIC SC3)の国際ワーキンググループの委員としても活動。
インフォセックアドバイザリー株式会社
東京都港区に本社を置き、サイバーセキュリティのアドバイザリー事業を手掛ける。主に中堅から大手企業向けに、サイバーセキュリティ診断、認証資格取得支援、セキュリティに特化したプロジェクトマネジメント(PM/PMO)を提供し、グローバル案件への対応を強みとする。また、IAPP(国際プライバシープロフェッショナル協会)、日本クラウドセキュリティアライアンス、サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアムの法人会員として活動している。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)