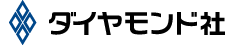インド人は悩まない
「考えすぎ」から解放される究極の合理思考
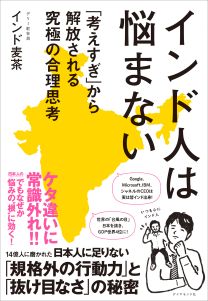
インド人は悩まない
「考えすぎ」から解放される究極の合理思考
書籍情報
- インド麦茶 著
- 定価:1727円(本体1570円+税10%)
- 発行年月:2025年10月
- 判型/造本:46並
- 頁数:272
- ISBN:9784478122204
内容紹介
日本人は悩むけど、インド人は悩まない! 日本を抜きGDP4位へ爆進中、14億人のインド式「悩まない」「考えすぎない」合理的思考を手に入れる一冊。「まずやってみる」DO文化、見た目重視のハッタリ文化、他人を使い倒す下請け文化…ひたすら自分のために人生を生きる習慣を紹介。皆、心にインド人を宿そう!
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに
超・格差社会で、合理的に力強く生き抜く14億人
ひたすら自分のために人生を生きるインド民たち
日本人の根っこは変えずに、悩みを〝技術的に〟克服する
序章 初学者のための インドを捉える3つの視点
「自分が生き残るための最適戦略」をとるインド民
POINT1 一つの国ではなく「人間がうじゃうじゃいる地域」
インドはヨーロッパ・アフリカと並ぶ「地域」
「多様」── ひとくくりにできない文化・言語・食
「分断」── 縦にも横にもある〝分断〟
「過密」── 人口14億人、世界の約6人に1人が密集する
「残酷な生存競争」── 人が大量に余っている国、出生数は日本の30倍
「強烈な生存本能」── 環境に最適化された精神性
POINT2 世界には「印僑」と「インド民」という異なる人々がいる
「インド民」にこそ宿る究極の合理思考
「インド民」=ジャイアンの「規格外の行動力」+スネ夫の「抜け目なさ」
先進国の常識では測れないビジネススタイル
「インド民の常識」に違和感を持つ印僑
POINT3 「用法・用量」を守って、インドから学ぶ
「毒にも薬にもなる」インド世界の思考
それでもインドは「世界の台風の目」
本書のパスポート
Ⅰ 「基礎」の部
第1章 「悩まない」心を手にする4STEP
インド民の「図太いメンタル」を取り込もう
STEP1 「悩まないインド民の存在」を知る
「自分のため」を徹底追求するメンタリティ
インドあるある① 飛行機が着陸した瞬間にベルトを外しはじめる
インドあるある② どこにいても何かしらの騒音がする
インドあるある③ 金の無心を「みっともない」と思わない
インドあるある④ 引き継ぎはサクッと、退職もさらっと
自分を守れない人は他人も守れない
STEP2 「命の価値の低さ」を直視する
実力がなくても「根拠なき過剰な自信」を持つ人々
幼少期に「徹底的に甘やかされる」
いともたやすく人間が生まれ、そして死んでいく
人間はみな小さな塵
STEP3 「それでも僕は悪くない思考」と「悩みを整理する思考」の両輪を手にする
「全て他人のせい」にすれば悩みは消える A面:他責思考
なぜインドでは「他責思考」が合理的なのか?
「全ての悩みは迷妄によって起こる」 B面:観察・分析思考
「観察・分析思考」は日本でも使える
「両輪のアプローチ」で心の平穏を手にしよう
STEP4 インドのDO文化を知り、「考えすぎ」から解放される
「こう思われたらどうしよう」── 日本人特有の「お察し」GUESS文化
「怒られたら、その時考える」── インドでは合理的なDO文化
「DO文化」を真似するな!
「まず、声を上げる」── 中庸としての「尋ねる」ASK文化
「ASK1回」で、悩みが1つ確実に減る
コラム 物乞いは無視が基本。しかし施さねばならない「あるもの」
Ⅱ 「攻め」の部
第2章 「言い訳に打ち負けない主張」で〝攻める〟
基本 要求を通すために「世界一の反撃力」を手にしよう
言い訳に負けると「あなた」と「家族」が損をする
「負けを認めると貧困が訪れる」社会での合理的行動
「5つの言い訳パターン」を知り、攻め返す
① 責任転嫁 問題発生の原因を別の所へ持って行く
Case1 チケットが取れていない
基本原則:相手の議論に乗ってはいけない
対処法 「できてない事実」に絞り、淡々と詰める
② 相殺消去 あなたに落ち度がある別の話題を持ち出して、おあいこを狙う
Case2-1 お客の発注を見過ごした
対処法 ブレずに相手に責任を問う
Case2-2 遅刻してきたドライバー
対処法 「それとこれは別の話だ」と伝える
③ 話題転換 全く関係ないトピックを説明し始め、論点をうやむやにする
Case3 担当者の調整ミスと多忙な工場長
対処法 相手の話を無視して、戻す
④ 因果改謬 因果関係のないことを、さも原因・理由かのように使う
Case4 地域ごとネットワークがダウンした
対処法 証拠を残す
⑤ 解決消去 あくまで非を認めず問題を即解決して、起きていなかったことにする
Case5 荷物が間に合わない
対処法 解決すればいいわけではない
第3章 ハッタリと見かけ倒しで〝攻める〟
合理的で効果的な「外面」の技術
基本 「見た目第一主義」は意外と効く
人間関係のほとんどは「短期決戦」
見た目が良ければ「中身は二の次」
「見た目も実力のうち」がインドの思考法
① 意見を通したいなら「とにかくしゃべる」
発言は、中身より「回数」と「場の支配時間」
「議論の中心にいる」イメージを植え付けよう
② 断定する。低く、大きな声で。
「思う」「感じる」では何も前に進まない
「物理的に迫力のある声」が説得力を生む
③ ナイスな身体に鍛えあげる。オシャレでアピールする
インド民のあからさまなマッチョ趣味
「豊かな体格」は動物的な感覚に訴える
地位を示す「贅沢品」でハッタリをかます
④「とにかく流暢」な英語を操る
「英語が上手い」も〝外見〟の1つ
日本人を悩ませる「英語コンプレックス」
⑤「知性的に見えるうんちく」を披露しまくる
「知らないことを知っている」人になる
コラム 「アイロンおじさん」とツケ払い文化
Ⅲ 「守り」の部
第4章 「ほんまかいな」の疑う習慣で自分を〝守る〟
物事を真っ当に疑う心を持つ
基本 「健全な猜疑心」を鍛える
インドでは「疑わないと幸せを守りきれない」
インド民も「インド民の言うこと」は信じない
日本人こそ、「健全な猜疑心」を持とう
他人を疑うには思考のトレーニングが必要
POINT1 「便益の先行販売」をされていないか?
Case1 遺跡を積極的に案内してくれる野良ガイド
対策 好意ではなく「収奪」目的だと理解する
POINT2 「情報格差」を狙われていないか?
Case2 博物館の前にいる親切そうな老紳士
対策 「自分が情報不足である」ことを認知する
POINT3 不本意に「選択を制限」されていないか?
Case3 一見やさしいタクシー運転手
対策 不必要に思える確認でも、する
POINT4 「仮想利益」を押し付けられていないか?
Case4 大変な仕事を自ら引き受ける従業員
「自ら不利益を取る」にはウラがある
コラム インドの病院で抜かれた「血」の行方
Ⅳ 「楽をする」部
第5章 他人を使って、もっと〝楽をする〟
個人の力は「たかが知れている」
「他人の使い方」は、インド民を見習おう
STEP1 次から次へと他人に任せる「インド的下請け文化」を知る
「全員がラクしようする」下請けスパイラル
Case 日本の飲食スタッフは実質「インド人10人分」
「流れてくる仕事」を止めると重荷を背負う
最上層から下層まで「下請け文化」が染みわたる
STEP2 「資本主義」は「他人を使うこと」と理解する
あなたが苦労をしても、「稼ぎ」とは一切関係しない
誰もが何かを下請けに出している
「他人をこき使う」才能にあふれるインド民
徹底的に仕組みを作り、他人を使う
STEP3 「日本的職人文化」の束縛から自由になる
「職人文化」と「下請け文化」は正反対
「他人任せ」は手抜きではない
コラム 家電の修理は我慢が肝心
第6章 家族を使って、もっと〝楽をする〟
家族は「楽をするために使えるツール」
まず「家族の利用価値」を測定しよう
STEP1 「不必要に自立しなくていい」と気づく
過剰に「家族ファースト」なインド民
日本人も「家族」をしたたかに使うと有利
STEP2 「家族の5つの利用価値」を知る
STEP3 家族関係を「判定式」で選び切る
家族という〝大きな船〟に「乗るか?」の判定式
「印僑」が「インドに戻りたくない」と口を揃える理由
家族を「戦略資産」として捉える
コラム インドにおける子どもの性別
Ⅴ 「回帰」の部
第7章 インド民から学ぶ合理性と日本人の美徳の融合
「ただの自分勝手なクソ野郎」にならないために
「サイドミラー・バックミラー」が必須
REMIND1 「インド民化」を防ぐ10のリストを活用する
「インド民化」の進行には自覚症状がない
「インド」に過剰適応すると倫理観が歪む
インドに居ずして「インド民化」していないか?
REMIND2 合理的なインド民にも弱点がある
「記録を軽視してテキトーに口伝する」 組織化が苦手な風土
「スケジュール管理の脆弱性」 時間に対するリスペクトの欠如
改善には程遠い衛生状態 「繰り返される下請け」の悪影響
「他人任せの連続」ゆえに育たない超一流の製品とサービス
REMIND3 日本人の素晴らしさを客観視する
①「他人のことを考えられる」民族性
② 世界で積み重ねられた日本人の信用
③ 安くてうまい寿司が食べられる「一流の衛生管理」
④「みんなのものを大事に扱う」精神性・美意識
FINAL 「和魂印才」の思考法を手に入れる
「こんなにいい国なのに、なぜインドを嫌がるんですか?」
日本人はムダに幸せから遠のいている
インド民は、より苛烈な社会で、より強く生き抜いている
「和魂印才」の生き方を身につける
心の中にインド民を一人置いておく
おわりに
参考文献
著者
インド麦茶
インド・デリー支社駐在員
10年以上インドを含めたアジア地域の事業に携わった後、インドに着任。全社規模のインド戦略の立案に携わり、複数の数十億円規模のインド案件を支援する。
インド人部下のマネジメントやオペレーション改善に従事する中で、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える“インド民”が織りなす“異世界”に困惑する。
日本の常識では測れない日々の中で、「彼らを分析して、騙されたり翻弄されたりすることなく立ち向かってやろう」と決意。駐在生活の傍ら「彼らの思考や生態を解明する」異文化フィールドワークをスタートする。
総人口約14億人(世界の6人に1人)の上位1%が富の40%以上を所有する超競争・過密・格差社会の実像に迫るうちに、「命の価値の小さい社会」で生きようともがくインド民の切ない実情や「力強さ」「彼らなりの合理性」に気づく。
同時に「礼儀正しく優秀なはずの日本人が、必要以上に日々、考えすぎ、思い悩んでいること」に疑問を持つようになる。インド民との対峙の日々から、日本人が幸せを謳歌するためのヒントを見出す。
インド民の生態を鋭い観察眼で研究・分析したnoteは、1年足らずで30万ビュワーを超える。2024年に公開した「インド民の代表的言い訳とその対応」でnote創作大賞2024ビジネス部門入選。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)