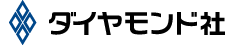チームプレーの天才
誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること
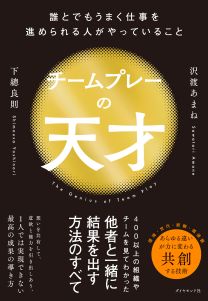
チームプレーの天才
誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること
書籍情報
- 沢渡 あまね 著/下總 良則 著
- 定価:1980円(本体1800円+税10%)
- 発行年月:2025年10月
- 判型/造本:46並
- 頁数:368
- ISBN:9784478122396
内容紹介
本当に仕事ができる人は「自分一人」で頑張りません。過去の成功法則が通用しない現代では、他者と上手に手を組み、互いの知識や能力を引き出し合う働き方が求められます。権力やお金で相手を動かすのではなく、フラットにつながりある「共創」の関係へ。そのために必要な全技術を詰め込みました!
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに ── かつてチームプレーと呼ばれたものと、これからのチームプレー
PROLOGUE │ 波乱の幕開け
第1章 「ゴールイメージ」を合わせる ── 見ている「景色」がバラバラになっていないか?
01 自分たちの「ビジョン」を見つめる
02 「3方向地図」を描いてみる
03 「メリット」または「世界観」でつながる
04 チームと個人の「接点」を見つける
column 自分の葬式の弔辞で、あなたは何と語られたいか?
05 与えられた言葉を「自分たちの言葉」に再編集する
06 「未来のプレスリリース」を書いてみる
07 「ファシリテータ」を起用する
08 日々の発信と受信で「軌道修正」する
STORY │ 注がれる「疑いの眼差し」
第2章 「動機」に寄り添う ── 自分たちの都合ややり方を押し付けていないか?
09 様々な「関わり方」を許容する
10 何でもかんでも「公式活動」にしない
11 まずは「外の世界」に慣れてもらう
12 「ゲスト」を呼んで外との交流をつくる
13 「ゆるいつながり」から始める
14 進め方の「型」を最初に決めておく
15 無駄な「事務作業」を押し付けない
16 「できないこと」を開示して、わかり合う
17 「主役」だけが目立ちすぎないようにする
18 「ここには敵がいない」と思える環境を創る
19 他者を「リスペクト」する意識を根底に持つ
column 誰に対してもリスペクトを忘れないこと
20 リスペクト意識を「すべての関係者」に醸成する
STORY │ プロジェクトの腰を折る「1通のメール」
第3章 「ストーリー」を描く ── 自分たちだけで盛り上がって「孤立」していないか?
21 「説得」ではなく「納得」で巻き込む
22 「3つのストーリー」を大事にする
column リソースのない私たちが、豪華ゲストを招致できている理由
23 「作り手」こそ、相手のストーリーに敏感になろう
24 ストーリーを「自分の言葉」で語る機会をつくる
25 「偶然のストーリー」に目を向けて、受け入れる
26 チームの「コンセプト」をブランディングする
column チームの「コンセプト」が、ブランドとなって人を惹きつける
27 チームのブランドを「内」と「外」に伝える
column いちばん身近で、いちばん強力な「ファン」は誰か
28 「5つの着眼点」で伝え方を考える
column ゆうこすに学ぶ、相手に興味を持ってもらうアプローチの心得
29 社内文書の「タイトル」にメッセージを込める
30 活動の「過程」から、記録・発信していく
31 2割の「動かない人たち」に振り回されない
32 「無関心な人たち」を無理に振り向かせようとしない
33 ときには「排他戦略」も実施する
STORY │「コワーキングスペース」って何?
第4章 「体験」を創る ──「本当にできるの?」と不安になっていないか?
34 「体験」と「場」が、理解と確信をもたらす
35 まずは「対話できる場」を創る
36 「サードプレイス」を活用する
37 まずは「小規模」で始める
column 小さなチームによる積み重ねが、大きな成功をもたらす
38 場を「実験場」として開放する
39 「偶然の出会い」を誘発する
column 創業113年の企業が共創のためにつくったサードプレイス
40 外にある「場」に出向いてみる
41 1人よりも「みんな」で体験する
column 「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」という体験のデザイン
42 場を「コミュニティ」に発展させる
43 コミュニティに「適した人」を見極める
44 場を中心に「コト」を創る
45 「プロダクト」を活用して体験を創る
46 イベントの目的化には要注意
47 ハンドルを「握る」「手離す」体験を創る
48 体験とインプットに「多様性」をもたらす
STORY │ 体験はしたものの、その先が見えない……
第5章 「振り返り」を習慣にする ──「勉強になった」「大変だった」で終わりにしていないか?
49 体験をした後は、必ず「振り返る」
50 「振り返りポイント」をあらかじめ設定する
51 「振り返り方」を設計する
column なぜ「振り返り」の習慣が、就職内定率を向上させたのか
52 体験を「問い」に編集して未来に目を向ける
53 学んだことをなんでもすぐ活かそうと焦らない
54 振り返りに役立つ「フレームワーク」を活用する
55 「意外な発見」を言語化する
56 想定外から生まれた「感動」を言語化する
column あなただけの「感動」が、閃きと価値を生む
57 暗黙知を「形式知」に変えていく
58 自分たちが提供できるナレッジやリソースを開示する
STORY │ いったい、いつになったら成果が出るの?
第6章 「余白」を大切にする ── 常に目先の「成果」を出すことだけに追われていないか?
59 「成果」をすぐに求めない
60 「生産性」の種類を見極める
61 「ネガティブ・ケイパビリティ」の姿勢も大事にする
column 「失敗する権利」について
62 未来を考えるための「余白」があるか?
63 余白を通常業務に「ビルトイン」する
column 「パタゴニア」が実践する、余白を持ち続けるための思想
64 まずは陰でこっそり始めてみる
column デザイン思考の核を成す「ラピッドプロトタイピング」の考え方
65 「遊んでいる」と思われないようにする
66 先駆者たちの活動に相乗りする
STORY │ チームに必要な「役割」って何?
第7章 「能力」を補う ── いまのメンバーのままで走りきれるだろうか?
67 チームに「足りないもの」を補う2つの方法
68 4つの「役割」をチームにアサインする
column 「地域の人を頼る」という共創のカタチ
69 「ライトプロジェクトマネジメント」を実践してみる
70 「優秀な事務方」をアサインする
71 「日程調整ストレス」を軽視してはいけない
72 越境して「外の世界」にいる仲間を見つける
73 「複業」や「兼業」を活用する
74 「中の人」「外の人」「さすらいの旅人」を加える
75 「渇き」によって内発的に動機づけする
76 「公式」と「非公式」な学びを組み合わせる
77 「学び」の機会を通常業務に組み込む
78 楽しく学ぶ場を創る
79 答えを待つのではなく、自ら「問う」
80 学びは「後づけ」「種明かし」でもいい
STORY │ この活動は、自分の未来につながるの?
第8章 「キャリア」のイメージをもつ ── 自分やメンバーの「その後」を描けているか?
81 「チームのため」だけでは走りきれない
82 チームとメンバー、それぞれに歩み寄る
83 関わる人たちの「次のステップ」「近未来」を描く
84 ロールモデルを見つける、または自分がなる
column メンターになる存在は「年上」とは限らない
85 チームや役割の「名前」を変えてみる
86 「プロティアン・キャリア」の考え方を取り入れる
STORY │ 私たちの努力の結果、「これ」でいいのか?
第9章 「変化・成長」を実感する ── 目先の評価に惑わされて「成長」を見過ごしていないか?
87 「短期的な成果」以外にも目を向ける
column 中長期の変化が、ブランドとファンを創出する
88 変化やプロセスを発信する
89 「意外な収穫」に名前を付ける
90 「収益貢献」への実感をもつようにする
91 「場外」の収益にも目を向けてみる
92 「他者のものさし」を知り、「新たなものさし」をつくる
column 1通のメールが気づかせてくれた、自分の歩みが持つ「価値」
93 小さく褒め合う
column 称賛こそが、人の歩みを支える
STORY │ 私たちが手にした「成長」とは
おわりに ── 0でもない、100でもない、新たな価値を生み出すために
EPILOGUE │「チームプレーの天才」の正体
著者
沢渡あまね(さわたり・あまね)
作家/企業顧問(組織開発&ワークスタイル変革)。あまねキャリア株式会社CEO/一般社団法人ダム際ワーキング協会代表理事。一般社団法人プロティアン・キャリア協会認定アンバサダー。静岡県磐田市“学び×共創”アンバサダー。『越境学習の聖地・浜松』『あいしずHR』『読書ワーケーション』主宰。大手自動車会社、NTT データなどを経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。主な著書・共著書は『組織の体質を現場から変える100の方法』(ダイヤモンド社)、『新時代を生き抜く越境思考』『EXジャーニー』『バリューサイクル・マネジメント』『職場の問題地図』(いずれも技術評論社)、『「推される部署」になろう』(インプレス)など。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。
下總良則(しもうさ・よしのり)
東北工業大学准教授(デザイン経営分野)/usadesign代表/一般社団法人 デザイン経営研究所 代表理事/一般社団法人 RAC 理事。多摩美術大学を卒業後、商品企画担当者・プロダクトデザイナー、グラフィックデザイナーを経て、usadesignとして独立。フリーランスデザイナーとして、世界シェア第3位の広告代理店ピュブリシス傘下ビーコンコミュニケーションズや、ネクストユニコーンをはじめとするスタートアップ企業にジョインし、「デザインと経営学」をテーマに活動を広げる。ニューヨークで伝統ある国際グラフィックデザインアワード「Graphis Design Award」にて2023年に金賞を受賞し、ロゴ部門単独では世界第2位、日本からのエントリーの中では第1位を獲得。このほか、日本高等教育開発協会が審査した「コロナ禍でのICTを活用した新しい授業公募」にて、唯一の審査会全会一致事例として最優秀事例に採択され、日本の私立大学の中で第1位を獲得するなど、受賞多数。グロービス経営大学院修了MBA取得。著書に『インサイトブースト 経営戦略の効果を底上げするブランドデザインの基本』(ハガツサ)がある。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)