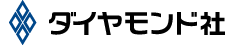忙しい人に読んでもらえる文章術

忙しい人に読んでもらえる文章術
書籍情報
- トッド・ロジャース 著/ジェシカ・ラスキー=フィンク 著/千葉 敏生 訳
- 定価:1980円(本体1800円+税10%)
- 発行年月:2025年09月
- 判型/造本:46並
- 頁数:252
- ISBN:9784478114926
内容紹介
ハーバード教授が行動科学の研究に基づき、文章の力が変わる「6つの原則」を解明!「少ないほどよい」「読みやすくする」「見やすくする」「書式を生かす」「読むべき理由を示す」「行動しやすくする」で伝わり方が劇的に変わる。メール、SNS、提案書、プレゼン……何にでも効果を発揮する、まったく新しい文章ガイド!
目次・著者紹介詳細を見る▼
目次
はじめに 科学に基づいた効果的な文章術
▪忙しい人の頭のなかでは何が起きている?
▪伝え方の「魔法」を手にする
▪「効果的な文章」とは何か?
▪毎日、情報の「滝」に膨大な時間を奪われている
▪1段落削るだけで、「80分」も浮く
▪読んでも「判断できない」文章の被害
▪「効果的な文章」を教わる機会がない
▪科学を根拠にした、まったく新しい文章術
PARTⅠ 読み手を理解する
CHAPTER1 「読み手の頭」はこうなっている
▪人間の「注意力」は限られている
▪私たちが「気づくもの」と「気づかないもの」
▪「コントラストが激しい要素」に真っ先に気づく ── 脳のショートカットその1
▪「選択的注意機能」をどこかに向ける ── 脳のショートカットその2
▪木に注目すると何が起こるか?
▪脳はすぐに疲れてしまう
▪この本を最後まで「一気に」読める?
▪作業をすばやく切り替えているだけ
▪脳は「2つの作業」で混乱する
▪相手にとって「優しい」文章を書くには?
CHAPTER2 「忙しい読み手」の視点で考える
▪読まれるための「4つの関門」
▪「読むかどうか」の関門
▪「後回し」の関門
▪「しっかり読むかどうか」の関門
▪「対応するかどうか」の関門
CHAPTER3 「自分の目的」を理解する
▪書く側が「自分の目的」を把握する
▪「誤植」が伝えるメッセージ
▪効果的に「推敲」する方法
▪「読んでもらえない責任」は書き手にある
PARTⅡ 6つの原則
CHAPTER4 第一の原則 少ないほどよい
▪「短くする手間」は結果的に効率がいい
▪「長文メール」は読まれない
▪長いと「情報が薄まる」
▪少なければ少ないほどよいのか?
「簡潔な文章」のルール
▪RULE1 「言葉」を減らす
▪RULE2 「内容」を減らす
▪RULE3 「依頼の数」を減らす
CHAPTER5 第二の原則 読みやすくする
▪「読みやすさ」を測るには?
▪「専門的な内容」も読みやすくできる
▪読みやすくすると「評価」される
▪読みやすい文章は「速く」読める
▪利用規約の読みにくさは「学術論文レベル」
「読みやすい文章」のルール
▪RULE1 「短くて一般的な言葉」を使う
▪RULE2 「ストレートな文章」を書く
▪RULE3 1文を「短く」する
▪「3つのルール」で読みやすくする
CHAPTER6 第三の原則 見やすくする
▪文章を「地図」としてとらえる
「見てわかる文章」のルール
▪RULE1 重要な情報が「一目でわかる」ようにする
▪RULE2 別々の内容は「分けて」書く
▪RULE3 「関連する内容」をまとめる
▪RULE4 内容を「優先順」に並べる
▪RULE5 「見出し」をつける
▪RULE6 「ビジュアル」を使う
▪「見てわかる文章」はこうつくる
CHAPTER7 第四の原則 書式を生かす
▪「コントラスト」で注目させる
「効果的な書式」のルール
▪RULE1 書式の意味を「読み手の期待」に合わせる
▪RULE2 もっとも重要な内容に太字、下線、ハイライトを使う
▪RULE3 書式を「むやみに」使わない
CHAPTER8 第五の原則 読むべき理由を示す
▪「これは読まなくては!」と思ってもらう
「自分ごとに感じさせる」ルール
▪RULE1 読み手にとっての「読む価値」を強調する
▪RULE2 「どういう人に読んでほしいか」を強調する
CHAPTER9 第六の原則 行動しやすくする
▪行動してもらうための文章
「実行しやすい依頼」のルール
▪RULE1 「行動のステップ」をシンプルにする
▪RULE2 「行動に必要な情報」をまとめる
▪RULE3 「集中力」をなるべく使わせない
PARTⅢ 原則を実践する
CHAPTER10 「効果的な文章」を書く
▪言いたいことが「たくさん」あるときは?
▪本書の原則は「もっと長い形式の文章」にも使えるか?
▪「同じくらい重要な情報」をいくつも伝えなければならないときは?
▪「情報だらけのメッセージ」を読んでもらうには?
▪「何度もやり取りが必要な場合」の注意点は?
▪「専門用語」を使いつつ6つの原則を実践することはできるか?
▪「多様な相手」に向けたメッセージを書くときの注意点は?
▪「送信者」を誰にするか?
▪メッセージを送る「最適なタイミング」は?
▪メッセージを送るのに「最適な手段」は?
▪「SNS」に適した書き方は?
▪「ハイパーリンク」の使い方は?
▪「皮肉、ユーモア、絵文字」は使ってもいい?
▪言葉の代わりに「絵や写真」を使ったほうがいいケースは?
CHAPTER11 「誰が誰に書くか」を意識する
▪「署名」を入れ替えるだけで印象が変わる
▪「堅い」ほうが信頼されるとき
▪「お元気ですか」を削るべきか?
▪「原則」は誰にでも役に立つ
▪わざとわかりにくく書く人たち
CHAPTER12 原則を定着させる
▪「人を助ける力」を得られる
▪「AI時代」にも生かせるスキル
謝辞
原文のまま掲載した文章の翻訳
原注/参考文献
著者
トッド・ロジャース(Todd Rogers)
ハーバード大学公共政策学教授。行動科学者。過去7年連続で同大学の教育賞を受賞。ハーバード大学行動洞察グループ・ディレクター。アナリスト・インスティテュートおよびエブリデイ・ラボ共同創設者。『ニューヨーク・タイムズ』『ワシントン・ポスト』『ロサンゼルス・タイムズ』など、さまざまな媒体で活躍している。
ジェシカ・ラスキー=フィンク(Jessica Lasky-Fink)
ハーバード・ケネディ・スクールに拠点を置くピープル・ラボのリサーチ・ディレクター。行動科学の知見を生かし、行政サービスの改善を中心に研究を行なっている。
訳者
千葉敏生(ちば・としお)
翻訳家。1979年、神奈川県生まれ。早稲田大学理工学部数理科学科卒。訳書に、キム『The Nvidia Way エヌビディアの流儀』、ミラー『半導体戦争』、キング『僕たちはまだ、インフレのことを何も知らない』、タレブ『反脆弱性(上・下)』(いずれもダイヤモンド社)、スティーヴンソン『トレーディング・ゲーム』(早川書房)、カーバー『ミステリー・パズル MURDLE』(実務教育出版)など。
電子書籍は下記のサイトでご購入いただけます。
(デジタル版では、プリント版と内容が一部異なる場合があります。また、著作権等の問題で一部ページが掲載されない場合があることを、あらかじめご了承ください。)